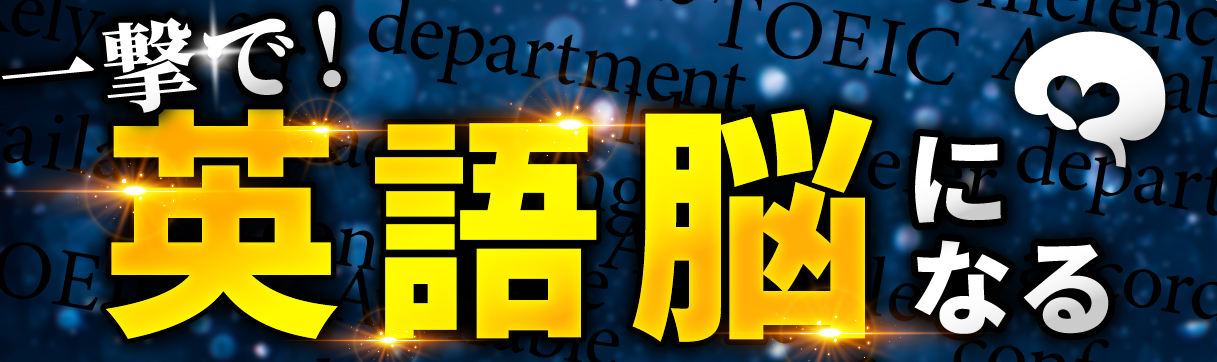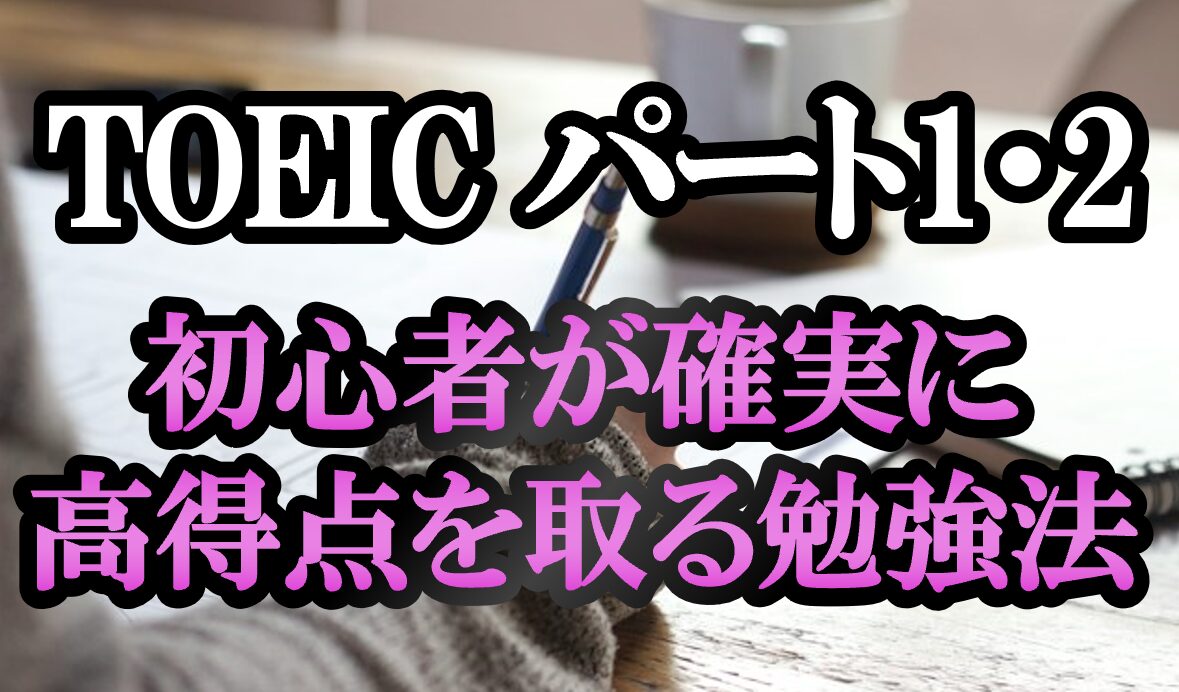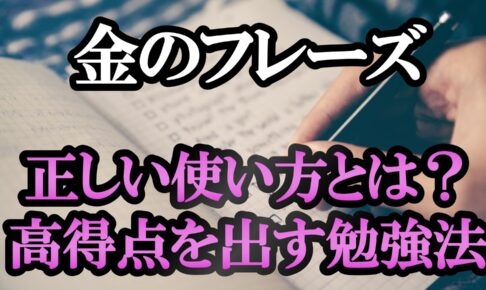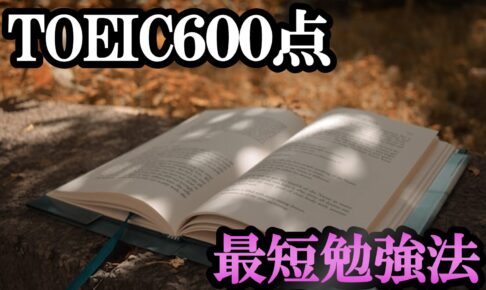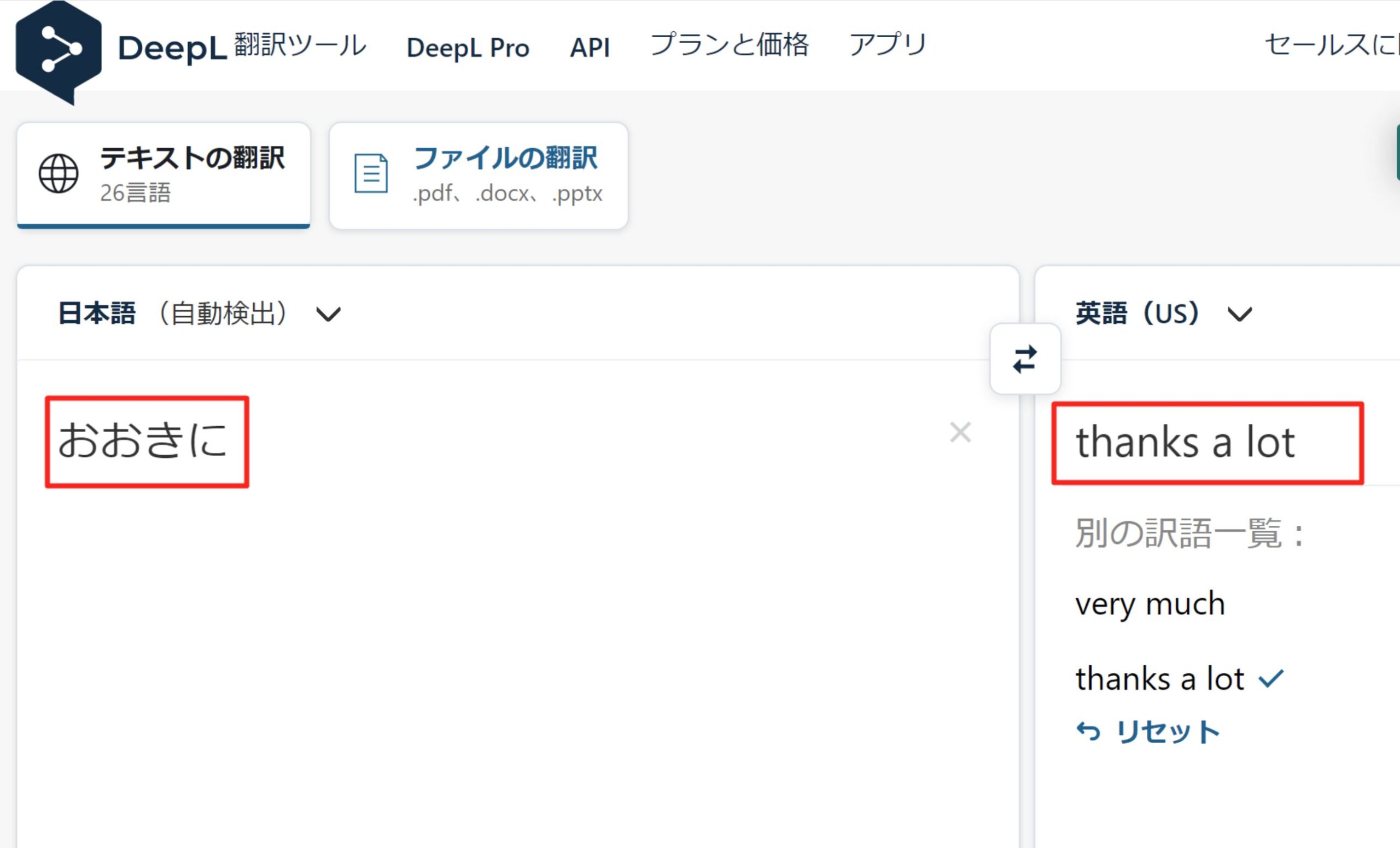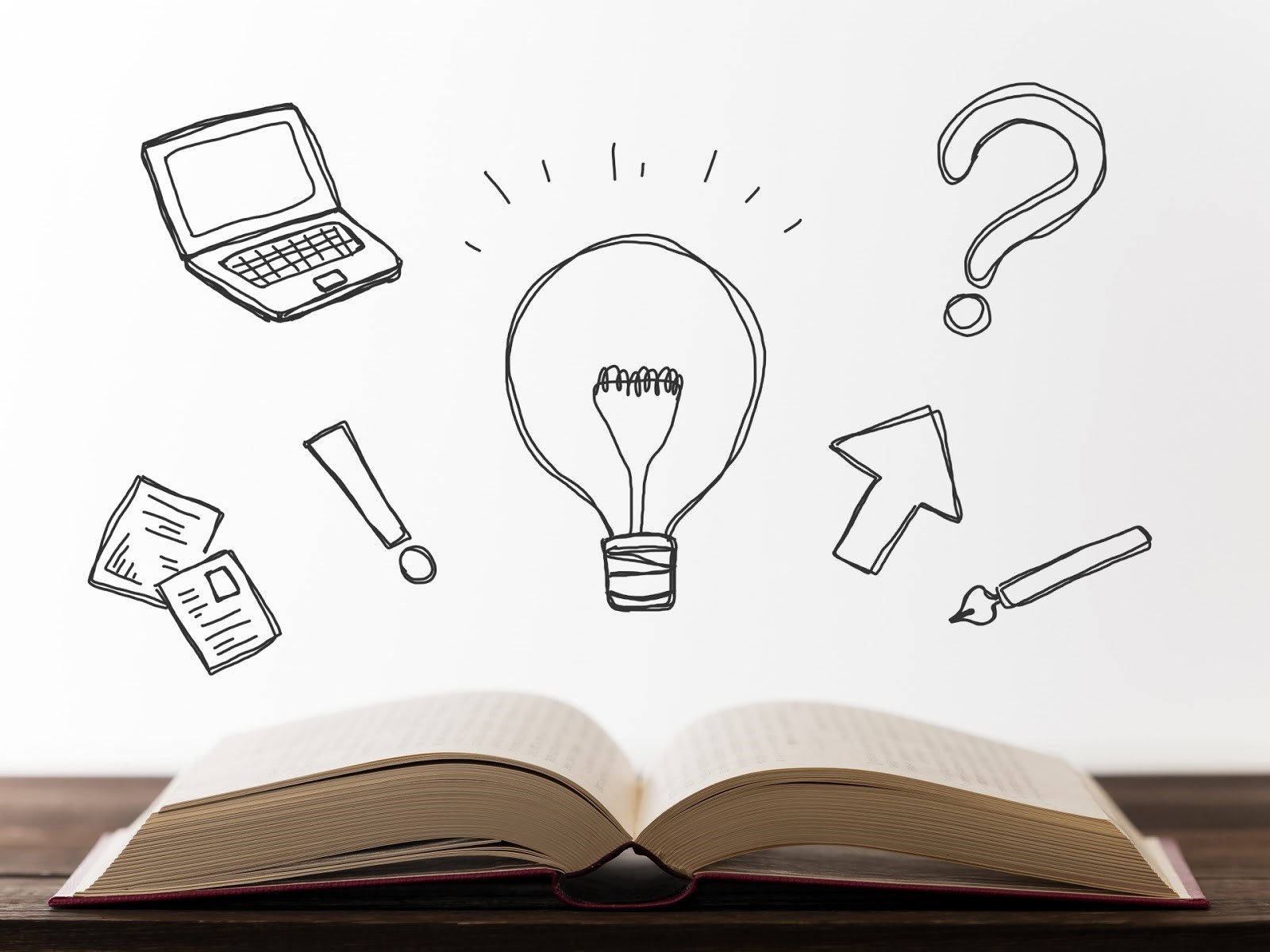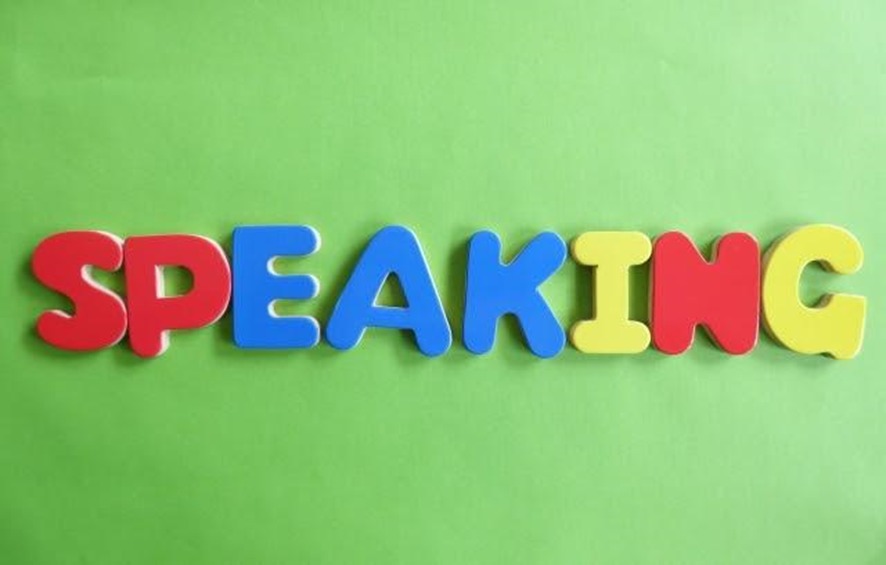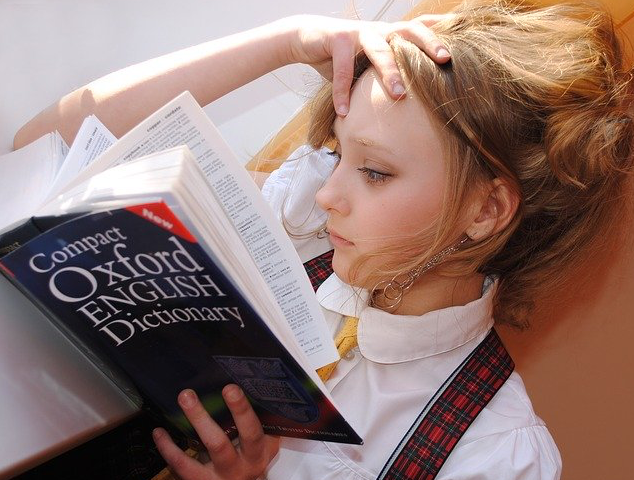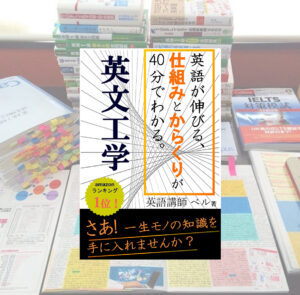目次

こんにちは、ベルです。
僕が短期間でTOEICの点数を底上げできたのは、
リスニングパートで高い点数をとれたことが大きかったです。
つまり、リスニング勉強法のコツを
知っている改知らないかで
大きくスコアが上下するとも言えます!
今回で高得点とれる知識を是非付けてください。
TOEIC初心者の場合、リスニングを極めれば、
簡単にTOEIC全体の点数をあげれます。
なので手っ取り早く点数を上げたいなら
リスニングから勉強をしていきましょう。
この記事であなたのTOEICのリスニングパートが
今までより確実に100点は上がります!
TOEICでリスニング対策するなら
まず始めにPart1と2で正答数を上げたいですね。
今回は、TOEICのPart1とPart2を最短で
高得点を取る方法の記事を書きました。
Part1と2だけを書くつもりだったんですが、
結局、リスニングについての本質的なことを説明したので、
リスニング全体的に活かせる方法です。
TOEICリスニングを解く時のコツ!
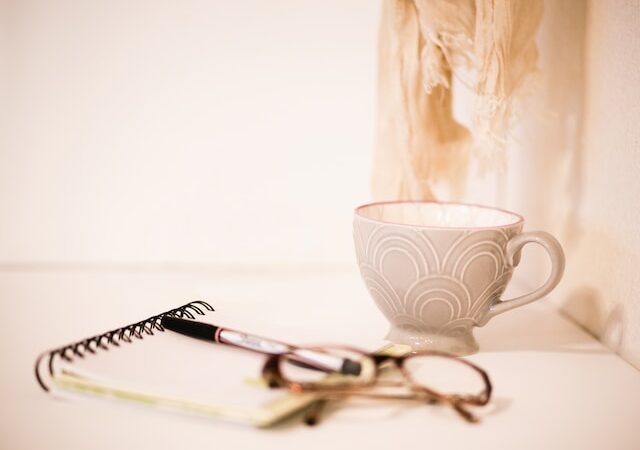
僕がTOEICを学ぶときは
「TOEICで点数を上げたければ、英語力よりもTOEICスコアだけ上がる勉強するべきだ!」
って思っちゃっていました。
TOEICスコアだけ上がる勉強っていうのは、
リスニングで流れてきた単語だけから推測して
「リスニング音声と同じ意味の選択肢があるから、この言い換えられた選択肢を選んでおこう!」
という問題の解き方をしちゃうんです。
「単語をピンポイントで聞き取ろうとする」
これやっちゃいがちなんですよ。
僕もそのような解き方をしていたんですが、
その解き方だと限界が来ました。
リスニングで高い点数を
狙うなら内容を理解しなければいけません。
内容が分かる解き方も説明しているので、
TOEIC以外にも応用しちゃいましょう!
取りたい目標点数レベル別の正答数
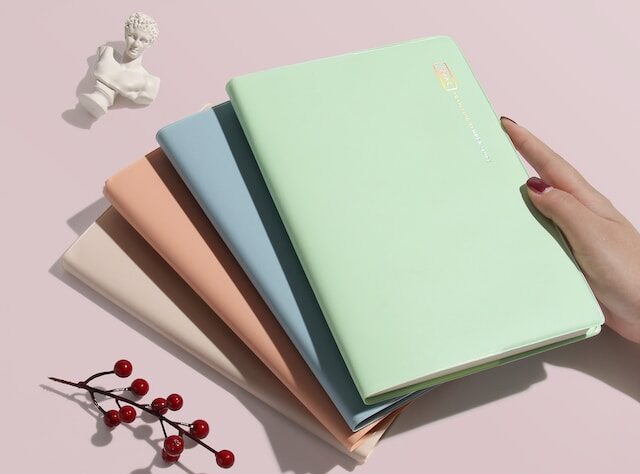
目標の点数ごとに正答数が変わってきます。
あなたの目標点数の場合ですと、
どのくらいの理解度があればいいのか把握しましょう。
目指すべき点数を把握しているだけで
日々の学習目標を正しく設定できます。
目標を設定したらその点数になるまで
繰り返し勉強をしましょう。
繰り返しの回数は各々の英語力で変わってきますが、
3回繰り返せばかなり力がついてきます。
(参照:All about)
900点以上の満点レベル
このレベルを目指す方は、
リスニングの内容の8割以上を
理解できているはずです。
そして問題が終わった後でも
問題の特徴を覚えていて、
「あ、あそこはコッチだった!」
と問題の復習を頭の中で出来ます。
つまり聞き取りはほぼ完璧でありゲシュタルトの設定をミスって勘違いから来るミスを直していく必要があります。
700点~800点
このレベルは6割~8割の
リスニング内容が聞こえています。
細かいところを理解していく必要があります。
それは、内容というよりもリスニングで省略されて発音している部分の原理を正しく理解するってことです。
リエゾンやリダクションと呼ばれている部分ですね。
リダクション・リエゾンについては
メルマガで解説しているので、
興味がある方はこちらからどうぞ。
600点以上
このレベルの人は、内容の大体半々
を理解出来ています。
だから質問文をリスニングの前からインプットしておけばリスニング文章の内容がより分かりやすくなるはずです。ちょっとしたコツで到達可能な点数でもあります。
600点以下
この点数から脱却するには、
覚えている(聞こえる)単語の
語彙が少ないかもしれないので、
まずは単語の勉強からスタートした方がいいかもしれません。
僕のおすすめは金のフレーズです。
使い方に不安がある方はぜひ記事を見てくださいね。
600点以下の時は、体質的に
英語をまだ受け入れていないかもしれません。
”リスニングの慣れ”が必要です。
リスニングについては、メルマガで紹介
しているので、興味があればリンクからどうぞ。
1か月で600点を取りたい方はこちらから
TOEICリスニングの頻出単語を知る

Part1,2はある一定のパターンが
あるので、そこさえ押さえておけば
勉強の時間を削減でき、効率が良くなります。
頻出単語は金のフレーズに100問
あるのでそれを使って、繰り返し
聞き取りして完璧にします。
単語の音が分かれば解ける問題ばかりです。
Part1,2は長文ではない分、
気を楽にして解けます。
その半面ミスした時に
ショックを感じてしまうパートでもあります。
リスニングの点数を劇的に上げる発音練習

リスニングの音が聞ける人は
発音できる人なんですよ。
だから、
正しく発音できなかったら
聞き取りは出来ません。
正しい発音についてはこちら
どんな音かいまいち分からない
ってときは、
リスニングの速度を
変えて練習するのもありだと思います。
金のフレーズなら専用アプリを使って
速度の変更も出来ます。
音が聞きずらいなら0.5倍速。
慣れてきたら1.5倍速。
などなど
緩急をつけて練習すると
効果的です。
早く倍速設定で聞き取るには
慣れないと難しいかもしれません。
日本語を1,5倍にして
聞き取るのは誰でも
できるので、日本語から
自信をつけていっても良いかもですね!
リスニングの点数を劇的に上げるシャドーイング

シャドーイングとは、
聞いた音声をそのまま
発声する勉強方法です。
同時通訳の方が好んで行う
練習方法でもあります。
シャドーイングは、話す聞くの
両面を同時にブラッシュアップ出来るため
リスニングの勉強において
最適といえます。
シャドイングについてはこちらの記事を参考にして下さい。
どこの国の英語が不得意か?
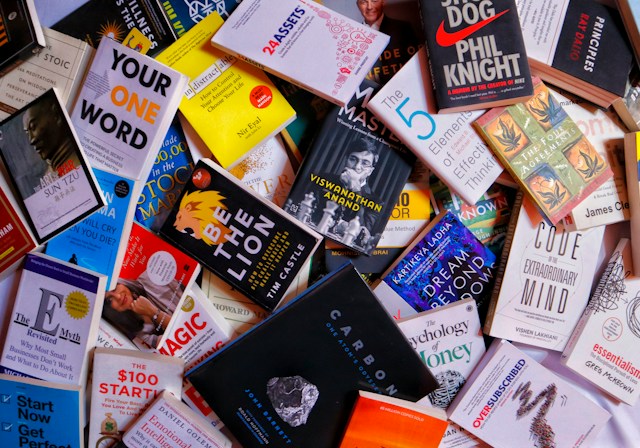
英語は一か所の国だけで話されてません。
TOEICでもアメリカ英語のみでなく
イギリス英語・オーストラリア英語・カナダ英語
が用いられて設問が用意されています。
この三種類ごとに微妙に発音のニュアンスが変わってきます。
TOEIC対策をするうえでも重要になってくる部分です。
あなたの苦手とする
英語が判明したら
繰り返しその言語で
学習して鍛えましょう。
詳しくはこちら(順次追加予定)
リスニング中に聞いた単語を忘れない方法

覚えたい単語があっても難しい日本語だったら
そもそも日本語から勉強しないといけないですよね。
日本人なのだから日本語なんて完璧!
って思うかもしれませんが、
日本人でも知らない日本語があれば
英語なんてわかるはずがありませんよね。
例えば、僕が金のフレーズで勉強していた時に
「天蓋」という単語が分かりませんでした。
「ほう。天蓋ね。」と単語だけで覚えてしまったら
実際のTOEICの試験で出てきた時に
答えられるはずが無いですよね。
だって、天蓋が何かわからないんだから
だから一度グーグルで天蓋の画像を検索してみました。
画像を探して「これが天蓋」と画像と一緒に結びつけれたら
深い記憶になるので、できれば画像で調べた方がいいですよ。
やり方は、簡単です。

このように知らない単語が出てきたら
言葉として覚えるのではなく、
画像と一緒に覚えるというのが大事になってきます。
それと、もう一つ深い記憶にする方法があります。
それは、一度間違えるという方法です。
僕の場合でいうと、「天蓋」は
フタっていう漢字を使っているから
テントのようなものかな?
と推測(仮定)します。
調べた結果、仮定は少しニュアンスが違っていました。
「あ~、天蓋はベッドの上に
付けるオシャレウェポンか!」
と気づけます。
だからこんな道筋ですね。
違った⇒恥ずかしい⇒正しく修正⇒忘れない
この道筋を自分の中でストーリを作ってもいいかもしれません。
例えば、
違った⇒お小遣いが減る⇒生命の危機⇒何が何でも覚える
のような脚本を自分の中で描いて、
単語を忘れないことを優先事項の第一
にするんです。
そうすれば、脳は別の何かを忘れることになっても
天蓋だけは忘れまい!と働くわけです。
この方法が忘れない脳の
作り方です。
TOEICリスニングPart1の勉強法
Part1は写真に写っている状況を
適切に説明している選択肢を
選ぶ問題です。
つまり、適切でなかったら
その選択肢はあり得ない
と言い換えれます。
消去法で考えていきましょう。
では、あり得ないとなるための
判断基準はどこですればいいのでしょうか。
それを3つに分けて説明していきます。
コツ①問題写真の確認
そもそも問題の写真の中に写っていない
単語が出てきたらその選択肢は、
100%あり得ません。
つまり、文章全体を把握しなくとも、
出てきた名詞だけで
答えを判断することも出来ます。
だから、Part1で出てきやすい
単語を金フレでカバーするのが
適しているんです。
コツ②動詞の時制
そして、Part1での問題は
現在進行形で言われることが
ほとんどです。
そのため、現在は行っていないけど
時制を変えたら連想してしまう
ひっかけ問題も頻出です。
しかし、ここで重要なことは、
写真での切り抜きのタイミングに
被写体が行っている動作を
答えないといけません。
このことに気が付くと、
名詞だけでなく、
動詞からも正誤判断が出来ます。
コツ③位置関係
あとは写真に写っている人・物の
位置関係ですね。
・隣り合っているのか
・向き合っているのか
・上下左右どこにあるのか
一列なら「in a row」
山積みなら「in piles」
寄りかかっている時は「lean against」
並んでいるなら「next to each other」
といった具合です。
これらのことを考慮して
例えば、店員がレジの前で
お客さんに飲み物を渡している写真。
この正解として必要とされる単語は、
(1)飲み物の単語⇒beverage
(2)渡している動作の動詞⇒hand,have
(3)2人の位置関係⇒face to face
(1)(2)(3)を問題を聞く前から
頭の中に単語を用意しておくと、
問題中も大分楽をして解くことが出来ます。
そうすれば選択肢をふるいにかけやすくなり
結果として、最適なものを選ぶだけで
正答率は高くなります。
つまり、Part1で大事なことは、
問題音声が流れる前の準備が
非常に大事になってきます。
準備がしっかりとしていたら
聞こえてきた音声が
瞬間的に頭の中でイメージとなります。
コツ④くくりが大きい単語を選ぶ
直接の表現だと、誰もが正解を取ってしまうため、
言い換え問題があります。
例えば、「車」を大きなくくりにすると「乗り物」です。
「電話」は「連絡をとる」です。
このように抽象的に言い換えられた単語が
出てきたら正解の可能性が高まります。
図で書くとこんなイメージですね。
車<<<<<乗り物
電話<<<<連絡をとる
ここで注意なんですが、
いくらくくりが大きいといっても
「all」が入った選択肢は
間違いであることが多いです。
だって、写真中のすべてを
カバーしてることってないですよね。
例えば
all the chairs
とリスニングが流れたとします。
すべての椅子を対象にすると
受験者の注意力も問題になってきます。
そんな能力は求められてはいません。
そのため、allが使われるときは、
正解ではないです。
TOEICリスニングPart2の勉強法
Part2は質疑応答問題ですね。
Qに対してAを答えている形の
Q&A形式です。
リスニングパートで点数をとれていない人に
ありがちなことが、
「そもそもQが聞こえない!」
っていう問題です。
問題が問題になっちゃうパターンですね。
この改善のために、先ほど書いたような
シャドイングをすると問題文の音声が聞けます。(理解できるとは違う)
音声が聞こえるようになれば
後は、ほんの少しの努力で理解まで落とし込めれます。
つまり、シャドイングして音声が聞こえるように訓練する。
音声が聞こえるようになったら理解するまで
繰り返し問題を解くってことです。
これについてはメルマガでも説明しているので
興味があればぜひ参考にしてみてください。
後は、ちょっとした4つのコツを知っていれば
Part2の対策に大手をかけれます。
コツ①:5W1Hで始まる質問文の時
5W1Hの疑問文の時の答え方に
Yes,Noで返答することはあり得ません。
そんな返しが来たときはラッキーですね。
選択肢を一つ減らすことが出来たわけです。
例えば、
Who~~~?
⇒Mike is.
「誰が~なの?」
という疑問文に対して
「それはマイクだよ!」
っていう返しの文章が普通です。
日本人だと答えるときに
「ハイ!それはマイクです!」
と答えるのが普通なので、
そこに付け込んだひっかけ問題です。
コツ②:文章の初めの部分に全力を注ぐ
Part2で文章の初めの単語を聞きそびれてしまうと、
絶対に正解にたどり着けません。
その根拠が分からなくなります。
だから、最初に
5W1Hなのか?
Doなのか?
付加疑問文なのか?
疑問文でない平叙分なのか?
というのを判断せねばなりません。
質問を聞いて、これまた忘れないように
何回か頭の中でループさせます。
「この質問はWhoだWhoだ」
な感じです。
始めの大事な部分を聞き取れたのに
選択肢を聞くことに夢中になり
質問の大義を忘れたら
本末転倒なので注意したいですね。
コツ③:否定疑問文が含まれた質問文の時
否定疑問文は
否定しているのか疑問なのか
よく分からなくてフワフワしていませんか?
本質的に否定疑問文は、
話し手が確実でないことを「~だったよね?」
なニュアンスで伝えるときに用います。
なので、答えは念押しの答えが多いです。
「~だったよね?」
⇒「そうそう。それは、マイクだったよ。」
⇒「いやいや、それはマイクだよ。」
という返答が適切になってきます。
これを英文にすると
Haven’t you ordered the new binders yet?
「もう新しいバインダーは注文したんだっけ?」
⇒Yes, I placed the order yesterday.
「昨日しときましたとも!」
(答えがYesなら中身もYesの内容になる。)
コツ④:質問文で出てきた単語は不正解であることが多い
質問文に出てきた単語は、
印象に残りやすいので、
製作者側も「ひっかけ問題」として
用意してきます。
TOEIC側はリスニングの内容を
聞けているのか?
という思惑を
逆に利用するパターンです。
同じように聞こえた単語は
注意深く考えてから選ぶようにしたらいいと思います。
最後に

リスニングで大事なことは、
あなた自身が発声できるかどうか
という点です。
発声が出来れば音が聞こえる。
この原理は英語の本質なので
必ず押さえておきたいです。
本質を抑えるためには経験が
必要なので今回紹介した内容を
日々の勉強に是非取り入れてみてください!
そして、回答に困ったときには
自分を信じて迷いなく
突き進んでいきましょう!
番外編:問題を聞いているうちに正解を忘れてしまう

問題を聞いている内に
「あれ?Aが正解だったっけ?Bだっけ?」
となり正解を見つけたはずなのに
忘れてしまうパターンですね。
あるあるですね。(笑)
僕も初受験の時は迷いました。
TOEICって書き込みダメ!?
チェックできないの!?
答え覚えないといけないの!?
と焦っているうちにTOEICは
終わってました。
そのあとの虚無感ハンパなかったです(笑)
だから、書き込みをしていけない問題文でなく、
解答用紙の方にチェックをしましょう。
問題は(A)から必ず順番に言われるので、
始め鉛筆を(A)に待機させます。
ここで、2つの選択肢があります。
適切な回答だった
/
/
(A)
\
\
不適切な回答だった
となります。
不適切な選択肢は鉛筆を横にスライドさせ(B)でも同じことをします。
適切な回答がきたら鉛筆を固定させ
最後の選択肢まで「違う!」
と判断出来て、初めて回答します。
こうすれば脳に余計な負荷をかけずに済みます。
問題を解く間は脳の負荷は極力減らすように
工夫が必要です。
このほかにも違った工夫があれば
教えてください!